虫歯の原因と予防、酸蝕症について
むし歯のできやすい場所
むし歯は次のような場所にできやすいとされています。
- 奥歯の窪みや溝(小窩裂溝)
- 歯と歯の間(隣接面)
- 歯と歯ぐきの境目(歯頸部)
痛みが無く、一見問題がなさそうに思える歯であっても、中でむし歯が広がっていることもあります。歯を長く残すためには、詳しい診査を受けて早期発見早期治療をする事が大切です。
- 奥歯の溝
- 歯と歯肉の境目
- 歯と歯の間(上から見るとむし歯がないように見えますが)
予防について
1)糖類摂取に気をつける
人が美味しいと感じる食べ物の多くは、お口の中の菌にも利用されやすく、特に糖類は虫歯や歯周病菌の大好物です。栄養のバランスを考えて、糖類が含まれているものを多く摂りすぎたり、長くお口に含むような事は避けるようにしましょう。
2) 細菌の塊である歯垢(プラーク)を取り除く
食後の歯磨きにより歯で増えた細菌の塊である歯垢(プラーク)を取り除いて下さい。歯垢染め出し液の活用や、「正しい歯磨き」の指導を受け、実施することも大切です。
※毎食後早めの歯磨きが良いという考え方が現在も一般的です。
歯垢を完全に取り除いた場合に再度成熟するため要する時間や、酸により高性能な顕微鏡で観察して歯の表面が僅かに荒れた場合に再石灰化が期待でき、それに要する時間、など様々な優れた研究が今もなされています。
それらの一部を強調して頻繁に歯を磨かなくて良い、であるとか、すぐ磨くのは良くない、といった論調も時々見られますが、それではなぜそもそも虫歯になるの?という疑問が残ります。多くの場合、食前に歯垢が完全に取り除かれている、とか、食後食べかすが全く残っていない、などの前提条件があるのです。
研究レベルの水準でお口の中に歯垢が全く無いというのは、極めて困難で現実的ではありませんし、多くの方が食後に食べかすがお口の中に残ります。また歯垢にはバイオフィルムとして、従来考えられているよりも複雑な働きをして歯に悪影響を及ぼすという研究も出てきています。
3) 歯を強くする
歯ができる時期にカルシウムなどの栄養を十分に取り、生えてきた歯には、お年寄りになるまでずっと口内用のフッ化物を利用 (塗布・洗口・歯磨剤)する事がむし歯予防に大変効果的です。むし歯になりにくい歯にしましょう。
4) 間食の時間を減らす
歯が1本でも口の中に出てきてから哺乳瓶にジュース(100%オレンジジュースやスポーツドリンクでも同様です)を入れて口に含んでいる事は、長時間糖を滞留させる事になり、歯に大変大きな損害を与えることになりかねません。また食事やおやつは決められた時間に取り、ダラダラとした何回もの間食で甘い物が口の中に残る時間が長くなることのないように気をつけて下さい。また、食べたらすぐ磨く習慣をつけ、歯垢が発育しないようにしましょう。
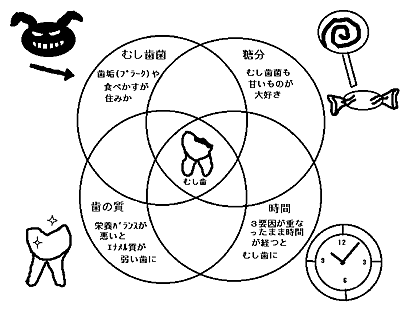
酸蝕症とは
酸蝕症とは、酸による歯の表面の脱灰(カルシウムが溶け出す)が起こり、むし歯(食物中の糖分が口の中の細菌によって酸に変化)と同様に歯が溶けることです。
強い酸性のガスのある特殊な環境下以外に、最近では、胃酸の逆流(つわり・逆流性食道炎・拒食症)やPH5.5以下の酸性の飲食物(柑橘類や酢、酸性飲料)を飲食することにより起こる側面も注目されてきています。
PH5.5以下の酸性の飲食物も飲みこんでしまえば口の中のPHは数秒単位で歯が溶けないレベルまで回復しますが、習慣的に頻繁に多量に摂取する、などの場合、酸蝕症となる危険性が増加します。
以下のPH値表は、田上順次 著:北迫勇一 (東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野)及び クインテッセンス出版(中島 郁)のご好意により掲載しております。
<参考文献>
●歯が溶ける!? 酸蝕歯って知っていますか?
監修:田上順次 著:北迫勇一 (東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野) クインテッセンス出版
●nico 2014年7月号 特集 飲食物で歯が溶ける?! クインテッセンス出版
フッ化物によるむし歯の予防について
フッ素(フッ化物)とはどのようなものですか?
フッ素は自然の中に広く分布している元素の1つです。地殼にある約90の元素中、13番目に豊富に含まれています。フッ素は元素単独では存在せず、フッ化物として螢石、水晶石、リン鉱石、などに多く含まれています。地中はもとより海水、河川水、植物動物などに微量ながら含まれており、量は異なるものの、私たちが食べたり飲んだりするものの中にも、必ずといっていいほど含まれています。
フッ化物はどうしてむし歯予防に有効なのですか?
フッ化物がむし歯予防に有効な理由は、次のような働きがあるからです。
1)歯の構造を強くする。(歯質の改善)
フッ化物が歯のエナメル質の表層に作用し、エナメル質の結晶構造を改善します。エナメル質は、ハイドロキシアパタイトの結晶によってできていて人体でもっとも硬い構造となっています。ところが、むし歯菌が産出する酸に対しては弱く、溶けてしまいます(脱灰)。フッ化物が作用すると、ハイドロキシアパタイトがフルオロアパタイトという酸に強い結晶構造となり、歯の表面が丈夫になります。
2)歯の表面を修復する。(再石灰化)
酸で表面が荒れたり、むし歯になりかかった(初期むし歯とも言われる:目に見える穴は開いていないが内部のカルシウムが溶けだして軟らかくなっている。歯科検診ではむし歯ではなく要観察歯とされます)エナメル質に作用し、その部分に再びカルシウム等が沈着して歯の表面が修復される事があります(再石灰化)。この修復はフッ化物が歯の表面にたくさんあると(歯の表面の濃度が高くなると)唾液中のカルシウム等を取り込む作用が働き、再石灰化が起こりやすくなります。
3)その他のフッ化物のはたらき
フッ化物は歯質を強くしたり、修復したりする作用以外にもむし歯菌による酸の産生を抑制したり、歯垢(細菌の塊)の形成を抑制する働きがあります。






